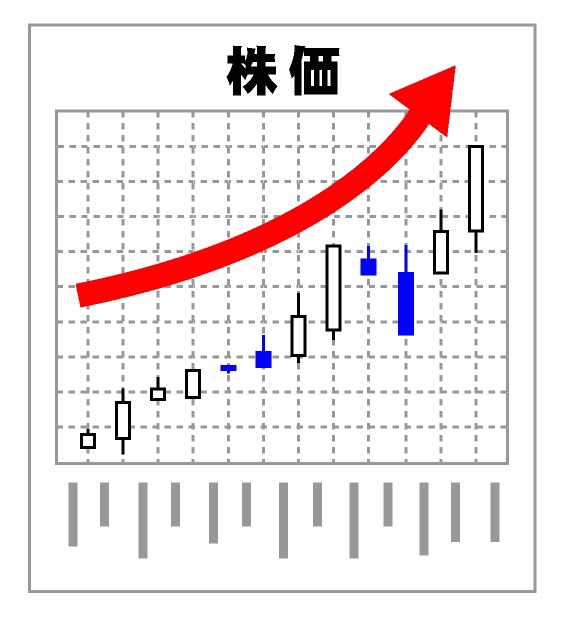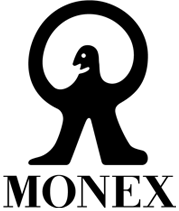昨日の記事で、単元未満株を貸株で運用する話をしました。どの証券会社が単元未満株の貸株サービスを展開しているのでしょうか。
単元未満株でも貸株金利がもらえる証券会社は?
結論から言いますね、今回、たまたま問い合わせをしたマネックス証券だけでした。単元未満株取引もやってるし、貸株サービスもあるけれども、単元未満株は貸株サービスの対象外という証券会社がほとんどでした。その中でも、マネックス証券はさすがです。
| 証券会社 | 単元未満株取引 (カッコ内は手数料) | 貸株サービス | 単元未満株 貸株サービス | ポイント投資(株式) | 移管出庫 手数料 |
| マネックス証券 | 〇 (52円) | 〇 | 〇 | × | 無料 |
| SBIネオモバイル証券 | 〇 (無料) | × | × | Tポイント | 無料 |
| SBI証券 | 〇 (55円) | 〇 | × | × | 無料 |
| 楽天証券 | × | 〇 | × | 楽天スーパーポイント | 無料 |
| auカブコム証券 | 〇 (52円) | 〇 | × | × | 1,100円(税込) |
| LINE証券 | 〇 (スプレッド方式) | × | × | LINEポイント | 1,100円(税込) |
| CONNECT | 〇 (無料チケット有) | × | × | Pontaポイント 永久不滅ポイント等 | 1,100円(税込) |
| SMBC日興証券 | △ (無料) | 〇 | × | dポイント | 1,100円(税込) |
ここまで見ていくと、①SBIネオモバイル証券で単元未満株に投資し、②出庫手続きでマネックス証券に移管、③マネックス証券で貸株サービスを利用するというのが、王道ですね。

貸株取引で気を付けること
貸株取引においては、留意しておくべき点がいくつかあります。
配当金、株主優待の受取設定
権利確定日に株式を貸出していると、配当金や株主優待を受けることができません。なので、配当金と株主優待を受取りたい場合は、権利確定日には貸株から外す必要があります。でも、ひと株ごとに権利確定日にオペレーションしていたら、大変ですよね。もっと言うと、3月末なんか、一日中証券会社の画面とにらめっこしなければならなくなります。
そんな面倒なことをしなくても、証券会社が自動的に権利確定日に合わせて、貸出した株を自動的に戻してくれます。マネックス証券では「当金自動取得サービス・株主優待設定」として設定することがでいます。細かい設定もできるようですが、一括で設定しておけば、まぁ、外れはないでしょう。
配当金をキチンと受取る設定をしないと何が起きるか。
配当金を受取る設定をしていないと、配当金相当額を証券会社の口座で受取ることになります。結果として、楽天銀行で配当金を受取れなくなるので、現金プレゼント企画の対象外となり、ポートフォリオの利回りが下がってしまいます。
あと、マネックス証券では、自動受取設定すると、その利用料として0.5%取られるので、便利さと利回りはトレードオフの関係となります。
長期保有者向け株主優待対策
貸株に出してしまうと、株主番号が変わるといわれています。株主番号が変わると、長期保有者向けの株主優待の対象外になっていしまうリスクがあります。これを避けるために保有株式の一部について、貸株に出さず、保有し続けることで同じ株主番号を維持し続けられないかなと考えてます(これから試してみます)。株主優待が100株からだとしたら、101株を保有し、100株は貸株に出して金利をもらい、配当・優待取得の自動設定で配当・優待の権利を取得します。ただし、1株だけは貸株のない証券会社においておけば、株式の継続保有になるので、株主番号は変わらないはず。今回、ヤマダ電機の株式を102株持つことになったので、100株は貸株に出し、残り2株は別の証券会社で持ち続けて、どうなるか検証してみます。
そもそも、単元未満株の取引のみであれば、あまり意識する必要はないと思います。
そもそも貸株とは、株価押下げ要因
貸株は株式を売りたい人に対して、証券会社を通じて貸出す行為です。金利を支払ってまで株式を借りたいという人は、信用取引で株式を売るわけです。金利よりも株価の下落のほうが大きいと考えているわけですね。したがって、高金利がついている株式ほど、市場では売りたい!と考えている人が多いので、株価は上がりにくいということになります。
自分が貸した株は市場で売られますので、その分、株価は押し下がると覚えておいてください。
まとめ
単元未満株の貸株サービスは、マネックス証券の一択!決まり!でも、単元株の貸株は楽天証券のほうが、経験則上、より多くの貸株金利をもらえるような気がしています。したがって、投資し始めから貸株に出すまでのサイクルをまとめると以下の通りになります。
- Tポイントを貯めてSBIネオモバイル証券でポイント使って株式投資
- 株式はマネックス証券に移管する。
- マネックス証券で貸株サービスを利用して、貸株金利を受取る。この時、配当金・株主優待の自動受取サービスの設定を忘れない。
- 株式を買増して単元株(例えば100株)になったら、そこで終わりではなくプラス1株(例えば101株)まで投資する。
- 101株(単元株+1株)のうち、100株(単元株)は楽天証券に移管して貸株で運用する。この時、配当・株主優待の金自動受取サービスの設定を忘れない。
- 残りの1株(単元未満株)は貸株サービスのない証券会社(例えばSBIネオモバイル証券)に残して、ずっと保有しておく。これで長期保有向け株主優待対策も完了。
少額分散投資は、チリも積もれば、という積み上げの繰返しです。また何か方策を探せたら記事にします。